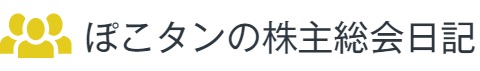マイクロ波化学 第18回定時株主総会
日時:2025年6月25日(水) 15:00-17:15(株主総会+事業説明会)
場所:大手町フィナンシャルシティグランキューブ(大手町駅直結)で開催、オンラインでのライブ参加
企業概要
マイクロ波化学(9227)
HP:マイクロ波化学株式会社 | マイクロ波で100年変わらなかった化学産業にイノベーションを
①「マイクロ波」を活用した独自のテクノロジーを開発。「何を作るか」ではなく「どのように作るか」に着目し、製造プロセスを化石資源由来の「熱と圧力」から電気由来の「マイクロ波」に置き換えることで、「省エネルギー」・「高効率」・「コンパクト」な環境対応型プロセスのグローバルスタンダード化を目指す技術プロバイダー。「デザイン力」および「要素技術群」からなる技術プラットフォームを駆使して、顧客課題に応じて、ラボ開発、実証開発といった研究開発フェーズから、実機製作、製造支援といった事業フェーズまでをワンストップでソリューションとして提供。炭素素材、ケミカルリサイクル、金属製錬・鉱山プロセス、電子材料、医薬品などの幅広い分野において研究開発のパイプライン拡充および事業開発活動を行う。
②筆頭株主は、社長の吉野巌さんで、125万株、7.9%を保有。
取締役の塚原保徳さんが、第2位の株主として、111万株、7.0%を保有。
三井化学(4183)が、第3位の株主として、77万株、4.9%を保有。
監査等委員である取締役の下條智也さんが、第7位の株主として、10万株、0.7%を保有。
③使用人数は、49名と少人数体制。
株式情報
時価総額:91億円(2025年6月24日時点)
売上高:16.0億円(2025年3月期実績)⇒16.1億円(2026年6月期予想、決算期変更により15ヶ月決算)
株価:579円(2025年6月24日時点)
1株純資産:67.1円(2025年3月末時点)、PBR:8.62倍
1株当期純利益:△55.7円(2026年6月期予想、決算期変更により15ヶ月決算)、PER:赤字
1株配当:無配(2026年3月期予想)、配当性向:無配
配当利回り:無配
株主数:16,526名
会計基準:日本会計基準
株主総会前の事前情報
①マイクロ波プロセスは、従来の「外部から」「間接的」「全体」にエネルギーを伝達するプロセスに対して、「内部から」「直接的」「ターゲットした物質」に効率的にエネルギーを伝達することが可能であり、エネルギー削減を実現することができる。さらに、2000年代以降、安価、かつ発電量が増えてきた自然エネルギー由来の電気と組み合わせた「電化」のプロセスとして大幅な二酸化炭素削減が可能であるため、カーボンニュートラル実現に向けた有望なキーテクノロジーとして注目されている。
②複数の化学企業と協業しながら、従来の製造プロセスを当社技術プラットフォームによって革新していく共同開発プロジェクトを進めている。当事業年度に推進した主要な開発プロジェクトは下記。
・金属製錬/鉱山プロセスにおけるマイクロ波を利用した標準ベンチ装置を完工。
・ニッケル鉱石の製錬技術に関する大平洋金属(5541)との共同開発において、マイクロ波標準ベンチ装置を用いたニッケル鉱石の煆焼および還元に成功。
・MiRESSOとの間でベリリウム製造実証におけるマイクロ波加熱反応器の設計および製造に関する業務委託契約を締結。
・鉱石製錬用のマイクロ波回転炉床炉の設計および製造に関する中外炉工業(1964)との戦略的提携を発表。
・南鳥島沖海底に存在するマンガンノジュール鉱石の製錬に関して、東京大学が採択された東京都の支援事業に参画し、マイクロ波を用いた鉱石の煆焼試験を開始。
・マイクロ波ケミカルリサイクルにおいて、「小型分散型」「連続式」の技術形態を検証することを目的として、連続運転可能な実証機を完工。
・レゾナック・ホールディングス(4004)と進めていた、使用済みプラを直接基礎化学品へ再生するケミカルリサイクルの共同開発において、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業」に採択され、技術開発を本格化。
③既存の開発案件を着実に進めつつ、新領域の開発案件獲得にも取り組んだ結果、当事業年度は、新規案件獲得数は通期計画29件に対して24件、契約済みの案件総数は通期計画61件に対して71件となった。 以上の結果、当事業年度における経営成績は、売上高1,608,403千円(前年比13.7%の減少)、営業利益187,394千円(前年比39.4%の増加)、経常利益182,126千円(前年比39.1%の増加)、当期純利益161,482千円(前年は944,895千円の純損失)となった。
④事業年度を「毎年4月1日から3月31日まで」から「毎年7月1日から6月30日まで」に変更するための定款変更を行うことを予定しており、これに伴って、経過期間である2026年6月期は2025年4月1日から2026年6月30日までの15ヶ月間の決算期間となる。2026年6月期については、前事業年度に引き続き「カーボンニュートラル」に貢献する開発テーマを中心に、顧客との共同開発を着実に進めていく。 2026年6月期業績予想としては、売上高1,613百万円、営業損失853百万円、経常損失864百万円、当期純損失884百万円を計画している。
原価については、Phase2案件における開発装置立上げ増加、および2025年3月期に設計などの利益率の高いスコープが先行したことによる計上タイミングの関係で、一時的に原価率が増加。販管費については、社会実装に向けた人員増強に伴う人件費増加、新規事業に係る先行研究開発投資により増加。2027年6月期は営業黒字化を計画とする。
⑤2025年5月9日開催の取締役会において、2025年6月25日に開催予定の第18回定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期(事業年度の末日)の変更を行うことを決議。当社の主要顧客の多くは3月期決算の国内企業であり、その予算確定時期が4月前後となるため、当社との共同開発案件に係る予算協議についても同時期に集中している。その結果、顧客との協議が業績予想の確定直前まで長期化し、一部案件については協議が未了のまま業績予想に反映させる必要が生じていた。こうした背景を踏まえ、6月期決算に変更することで、当社の予算策定スケジュールを3か月後ろ倒しとし、顧客との予算協議の結果を適切に反映できる環境を整備する。決算期変更の内容は、現在の毎年3月31日を変更後は毎年6月30日とする。決算期変更の経過期間となる第19期は、2025年4月1日から2026年6月30日までの15か月間となる予定。
⑥マイクロ波発振器の内製化を目指すプロジェクトを立ち上げ、公益財団法人横浜企業経営支援財団が運営している横浜新技術創造館リーディングベンチャープラザ(横浜市鶴見区)内に新たな研究拠点「横浜ラボ」を開設する。横浜ラボは、2025年7月1日から稼働を開始し、マイクロ波発振器の内製化を目指すプロジェクトの拠点となる。中期ビジョンに掲げる、鉱山プロセス、ケミカルリサイクルといった注力領域の「社会実装フェーズ」への移行を見据え、今後は高品質なマイクロ波発振器の安定供給体制の構築が不可欠となっている。また、加熱用途に特化したマイクロ波発振器の開発を通じて、コスト削減と普及促進を図ることも目的としている。2026年度末までにマイクロ波発振器の試作機完成を予定し、その後は本社ラボ・大阪事業所および各プロジェクトへの供給を開始する。さらに、量産体制が整い次第、外部販売も視野に入れている。当社は、マイクロ波発振器の内製化を通じて、「マイクロ波プロセスをグローバルスタンダードに」という当社ビジョンの実現に向け、歩みを進めていく。
⑦従来から取り組んできたマイクロ波ソリューション事業(提携事業)を中核としつつ、新規事業の創出を両輪とした成長戦略を展開。これにより、FY2030時点で売上高100億円の達成を目指す。これまで収益の中心であったPhase2案件(単価数千万円~)に加えて、単価数億円〜数十億円のPhase3(実機導入)を2030年までに5件実装させる–これによりFY30までの5年間で130〜140億円の売上を計画。
⑧実機導入による大型収益を目指すとともに、技術・装置の標準化を進めることで長期的な粗利率の改善・リードタイム短縮化を行う。また、マイクロ波装置のスケールアップに伴い発振器コストが増加し納期も長期化しており、提携事業における利益を圧迫していたことから、2026年6月期より内製化に向けた開発を進め、コストダウンを目指す。
⑨主要顧客である化学企業においては、新年度直前の3月までに研究開発予算の獲得が行われるため、当社との共同開発は第1四半期または第2四半期に開始することが多くなる。その結果、収益が計上される共同開発の完了時期が下半期に偏重する傾向にある。また、大型案件の完了時期による影響がある。これに対して販売費及び一般管理費は、その大部分が固定費であることから、利益の割合も下期に偏重する傾向にあり、投資家の判断に影響を及ぼす可能性がある。
⑩当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおり。なお、約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月以内で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれていない。
・共同開発契約共同開発契約においては、開発テーマに関する報告書やサンプルなどを提出し対価を得ている。このような契約においては、顧客による報告書やサンプルなどの検収が完了した時点で収益を認識している。
・ライセンス契約ライセンス契約においては、顧客に対して当社の知的財産の実施許諾を行い、その対価として契約一時金、ランニングロイヤリティを得ている。契約一時金は、知的財産の実施許諾する時点で収益を認識している。ランニングロイヤリティは、実施許諾先の企業の売上高に基づいて生じるものであり、実施許諾先の企業において製品が販売された時点で収益を認識している。
⑪当社の事業を捉える為の重要な経営指標は、1.新規契約獲得数、2.契約総数、3.Phase別売上高である。
⑫2025年3月期は、新規契約獲得数は計画29件に対して、24件で着地。契約総数は計画61件に対して、71件で着地。Phase別売上高はPhase1の進捗が遅れたが、Phase2は計画比+11%となり、売上高全体の83%を占める(2024年3月期は68%)。
⑬監査等委員である取締役と社外取締役を除く取締役2名の報酬等の総額は2,400万円。単純平均で取締役1人当たり1,200万円。
株主総会での個人メモ
①株主総会終了後に、事業説明会を開催。株主総会は15:15に終了し、15:30から事業説明会が開催された。
②株主総会での事業報告はほぼ割愛され、質疑応答での質問も無し。事業説明会で事業報告をしているように見えた。事業説明会では、多くの質問や意見が寄せられていた。
③質疑応答で、「リチウムに対する優位性は?」との旨の質問あり。「材料に使用する技術なので直接的な関係は無い。」との旨の回答。
④質疑応答で、「株主総会において、事業報告を省略し過ぎ。しっかりと対応したほうがよい。」との旨の意見あり。
⑤質疑応答で、「防衛産業に使用される技術なのか?」との質問あり。「防衛産業に使用されるという話は無い。」との回答。
⑥質疑応答で、「海外進出の計画はあるのか?」との質問あり。「海外のお客様はいるが、まだ海外にプラントは無い。」との説明。
⑦質疑応答で、「新しい取り組みについて、状況発信が足りていない。」との意見あり。「お客様との関係で秘密保持契約により開示できないことがある。」との回答。
⑧質疑応答で、「マイクロ波発振器の内製化は、本当にできるのか?」との質問あり。「上手くいかないこともあるかもしれないが、何かあれば報告する。為替の問題もあるので内製化を進めたい。」との説明。
⑨質疑応答で、「全個体電池でもリチウムが使用される。リチウム関連技術が使えるのでは?」との旨の質問あり。「使われる可能性が極めて高いと考えている。」との回答。
⑩質疑応答で、「グロース市場の上場維持についてどう考えているのか?」との質問あり。「大丈夫だと思っている。これから実装フェーズに入る。売上規模が一つ上っていき、業績も上っていく。」との説明。
⑪質疑応答で、「マイクロ波のエネルギー損失はどの程度なのか?」との質問あり。「電気からマイクロ波への転換でエネルギーが約70~80%程度となる。その後の損失はほぼ無い。一旦マイクロ波に転換されると、ほとんどのエネルギーが物質に転換される。」との回答。
⑫質疑応答で、「レアアースの精製への活用はできるのか?」との質問あり。「できる。」との説明。
⑬質疑応答で、「技術プラットフォームの拡大について、具体的な内容は?」との質問あり。「マイクロ波と親和性のある分野。具体的な内容は開示していない。」との回答。
⑭質疑応答で、「海外進出のターゲットとなる国は?」との質問あり。「鉱山プロセスのある南半球、自動車リサイクルのヨーロッパ。」との説明。
⑮質疑応答で、「低迷する株価についてどう考えているのか?」との質問あり。「事業を成長させ、市場の皆様に伝えることを愚直にやっていきたい。」との旨の回答。
⑯質疑応答で、「CO2以外の環境規制にもマイクロ波を使う意義はあるのか?」との質問あり。「CO2以外の環境規制については無い。」との説明。
⑰質疑応答で、「マイクロ波発振器の内製化は、横浜ではなく既存の大阪のほうがよいのでは?」との質問あり。「関東の方がインフラが整っている。」との回答。
⑱質疑応答で、「宇宙関連のマイクロ波活用について、具体的な内容は?」との質問あり。「JAXAとやっている。月や火星の氷を水に変える。」との説明。
⑲質疑応答で、「電力不足が事業の足枷となるのでは?」との質問あり。「電力事情は国策となる。鉱山については、パートナー企業が安定的に電力を確保している。」との回答。
⑳質疑応答で、「設計にAIを活用しているのか?」との質問あり。「設計に活用している。文献の検索やマーケティングにも活用している。」との説明。
㉑質疑応答で、「サウジアラビア関連の事業はあるのか?」との旨の質問あり。「何件か引き合いをもらっている。」との回答。
㉒質疑応答で、「通信衛星関連での事業展開は?」との旨の質問あり。「具体的なプロジェクトは無い。いくつか協議していることはある。」との説明。
㉓質疑応答で、「最大のライバル企業は?」との質問あり。「化学メーカーの物づくり全般。」との回答。
㉔質疑応答で、「金の特有の周波数は確認済みなのか?」との質問あり。「金の特有の周波数は見たことが無い。」との説明。
㉕質疑応答で、「マイクロ波発振器の内製化に、大きな設備投資が必要となるのでは?」との質問あり。「ファブレスでやっていく。」との回答。
㉖議案の採決方法は拍手での採決。
⇒議決権の過半数を保有する大株主もいない状況で、出席者により保有している議決権数も違うので、デジタル時代に会場の拍手の多数で賛否を決めるのでは基準が曖昧に感じる。投票方式を採用したりして、その場で数字で示したほうが株主総会に出席している株主から見て納得感がある。
株主総会を終えて感じたこと
株主総会時点、株式は未保有ですが、今回、オンラインでのライブ参加でしたが、実際に社長や取締役の振る舞いを確認できたこと、会社の雰囲気を感じられたこと大きなメリットでした。
株主総会終了後の事業説明会では、多くの質問や意見が寄せられ、社長の吉野巌さんと取締役の塚原保徳さんが丁寧に回答対応されていました。質問が尽きるまで対応されており、好印象でした。
質疑応答でも質問が出ていましたが、マイクロ波発振器の内製化を目指し横浜ラボを新設するものの、使用人数が49名と少人数なので、大阪の吹田ラボと2拠点に分かれる弊害が無いかやや気になります。
また、今期の業績予想が赤字となっている点も気になりますが、2027年6月期の営業黒字化計画が予定通り進みそうなのか、今後のIRを注視します。