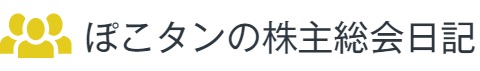ACCESS 臨時株主総会
日時:2025年11月19日(水) 10:00-10:25
場所:住友不動産秋葉原ビル(秋葉原駅徒歩3分)
出席株主数:約30名
お土産:無し
企業概要
ACCESS(4813)
①主として国内市場におけるIoT関連ソリューションおよびソフトウェアなどの提供を行う「IoT事業」(売上構成比59%)を主に、国内および海外市場における組み込みブラウザをはじめとしたWebプラットフォーム関連ソリューションなどの提供を行う「Webプラットフォーム事業」(売上構成比12%)、ネットワーク機器向けソフトウェアおよびホワイトボックス向け統合Network OSなどの提供を行う「ネットワーク事業」(売上構成比29%)を運営。
②筆頭株主は、清原達郎さんで、1,260万株、33.3%を保有。
第2位の株主は、NTT(9432)で、513万株、13.5%を保有。
第8位の株主は、スポーツウェアブランド「KJUS」日本総販売代理店のノースブレインで、36万株、0.9%を保有。
第10位の株主は、医薬品の研究・開発などを手掛けるブレストシーブで、28万株、0.7%を保有。
株式情報
時価総額:217億円(2025年11月18日時点)
売上高:159億円(2025年1月期実績)⇒205億円(2026年1月期予想)
株価:545円(2025年11月18日時点)
1株純資産:232円(2025年4月末時点)、PBR:2.34倍
1株当期純利益:△37.2円(2026年1月期予想)、PER:赤字
1株配当:無配(2026年1月期予想)、配当性向:無配
配当利回り:無配
株主数:10,664名
会計基準:日本会計基準
株主総会前の事前情報
①2026年1月期第2四半期は、当社グループはIoT事業においてプロフェッショナルサービスの積極的な事業拡大を図るとともに、Webプラットフォーム事業についてはTV・車載の双方の収益安定化に取り組んでいる。また、ネットワーク事業については、サービスプロバイダー向けの事業拡大を継続するとともに、今後も大きな成長が予想されるAI関連のデータセンター向けの案件パイプラインの構築と拡大に努めている。当中間連結会計期間においては、売上高は若干の増収であったものの、主にセグメント毎のセールスミックス・利益率の違いにより、前年と比較して大幅な減益となっている。以上の結果、当中間連結会計期間における連結業績は、売上高90億55百万円(前年比8.2%増)、営業損失19億89百万円(前年は営業損失6億53百万円)、経常損失22億52百万円(前年は経常損失3億52百万円)、親会社株主に帰属する中間純損失27億18百万円(前年は純損失4億95百万円)となった。
②IoT事業は、通信技術、クラウド技術、アプリ開発力、センシング技術などをワンストップで提供できる強みを活かし、企業のいかなるDX需要にも対応できるIoTプロフェッショナルサービスや、自社開発の各種IoTソリューションを主軸に事業展開している。また、アジア地域に進出する日本の通販事業者向けに、オムニチャネルでの販路拡大機能と物流などのバックオフィス機能を統合した業務支援クラウドサービス「CROS」の提供を行っている。当中間連結会計期間については、前年度から引き続き、主軸であるIoTプロフェッショナルサービスの事業拡大に向け、旺盛なDX投資需要を背景に位置情報の利活用やエネルギーマネジメント、生成AI関連などに係る案件への営業活動を推進している。業績面では、前年度に受注した案件の納品や顧客側でのサービス提供開始により売上高が前年同四半期比で大幅増となり、それに伴いセグメント利益も増益となった。外部顧客への売上高は5,275百万円(前年比94.9%増)、セグメント損益は384百万円(前年比762.0%増)となった。
③Webプラットフォーム事業は、ドイツ・中国・韓国に設置している現地法人と連携し、国内外の市場においてスマートデバイス、情報家電や各種デバイス向けに豊富な搭載実績を持つ高性能・高機能ウェブブラウザ「NetFront Browser」シリーズをはじめとした組み込みソフトウェア製品を提供しており、グローバルでのシェア拡大を推進している。また、中長期的な成長施策としてTV・放送および車載インフォテインメント用途向けにコンテンツや動画の配信システム・サービスプラットフォームの事業育成を図っている。当中間連結会計期間については、海外子会社において案件の進捗に伴う売上計上時期の変化もあったことや、国内におけるプロダクトのライセンス・ロイヤリティ収益が堅調に推移した影響もあり、前年比で売上高は増収となり、セグメント損益は黒字化した。外部顧客への売上高は1,120百万円(前年比19.1%増)、セグメント損益は96百万円(前年は△126百万円)となった。
④ネットワーク事業は、米国子会社IP Infusion Inc.を中核としてインドやカナダなどに開発拠点を設置しており、ネットワーク機器向け基盤ソフトウェア・プラットフォームの開発・提供から事業をスタートして現在はホワイトボックス向け統合Network OS「OcNOS」の事業拡大に注力している。ホワイトボックスは、更なる通信トラフィックの増加が見込まれる中、データセンター事業者、通信キャリア、IXP(インターネット相互接続ポイント)事業者などにおいてネットワークインフラ設備投資・運用コストを大幅に低減しつつ運用の自由度を高める有力な手段と目されており、世界的に市場が拡大しつつある。この様な環境の中、IP Infusion Inc.では通信事業者向けのCSR(Cell Site Router)やデータセンター、光転送システム(Routed Optical Networking)、ブロードバンドアグリゲーションなどの多用途に対応可能なホワイトボックスソリューションを展開している。また世界各地域において有力な事業基盤を有する大手ディストリビューターやグローバルSIerとの提携を通じ、通信事業者へのホワイトボックスソリューションやサポートなどの安定的な提供に取り組んでいる。当中間連結会計期間については、「OcNOS」における新規顧客獲得は堅調に推移したものの、前年同期での大型案件の反動などもあり、前年比で減収減益となった。外部顧客への売上高は2,659百万円(前年比△43.6%)、セグメント損益は△2,594百万円(前年は△578百万円)となった。
⑤当社グループは、過年度より継続的に営業損失を計上していたことに加え、前連結会計年度においては2024年10月15日以降の社内調査および2024年11月29日以降の特別調査に関連する調査費用も含め、多額の親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことにより、資金水準が低下傾向にある。また、当社グループは、特にネットワーク事業において事業成長に向けて継続的にソフトウェアの機能追加・改善のための研究開発費を投入しているが、他方で特定の大口顧客との取引に不確実性が残存しており、将来の売上高が当初見込みより減少するリスクがある。このような場合、営業活動によるキャッシュ・フローが減少し、当社グループ全体として資金繰りに関する懸念が生じることになることから、前連結会計年度末において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象が存在し、当中間連結会計期間末においても同様の状況が継続している。
⑥2025年6月30日に、「特別調査委員会より調査報告書を受領した。」と公表。2024年11月29日付「特別調査委員会設置及び2025年1月期第3四半期決算発表の延期ならびに2025年1月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表していたとおり、ネットワーク事業における新興顧客を中心として増加した売掛金の一部の回収期間の長期化の原因などを調査する過程において、当社米国子会社における一部取引について、不適切な売上計上の疑義が生じたため、網羅的かつ深度ある調査を実施するために当社と利害関係を有さない外部専門家を中心として構成される特別調査委員会を設置し、当社は事実関係の解明及び決算関連手続きの早期完了のため、特別調査委員会による調査に協力をしてきた。その後、当該調査の過程で本件疑義に類似する事案やソフトウェア資産に係る会計処理の適否に関する疑義が検出されたため、特別調査委員会には追加調査事項を含めた調査の実施を委嘱し特別調査を継続してきた。特別調査の結果、当社グループのネットワーク事業を主に担う連結子会社であるIP Infusion Inc.(米国子会社)において、以下の事実が判明した。「ソフトウェアのライセンスの販売取引に関し、本体契約と同時期に顧客をリスクフリーにするサイドレターを別途締結し、当該米国子会社が実質的にリスクを継続的に保持する条件となっていたにもかかわらず、本体契約のみに基づき売上を計上していたこと(売上高の過大計上)。」「ソフトウェアのライセンスの販売取引に関し、収益認識の条件が充足されていない状況であるにもかかわらず、虚偽の取引証憑や資料を作成して売上を計上していたこと(売上高の早期計上)。」「ソフトウェアの資産計上額の算定根拠となる集計データの内容区分に関する不適切な操作や、ソフトウェアの計上タイミングの根拠となる取引証憑の不適切な改変が行われており、その結果、過去に遡って当該米国子会社におけるソフトウェア資産計上額が過大計上であったこと(ソフトウェアの過大計上=研究開発費などの過少計上)。」これらは当該米国子会社の一部のマネジメント(内、1名は当社の取締役も兼務)が関与する形で進められたものであり、当社は、売上高の過大計上および早期計上、ならびにソフトウェアの過大計上、その他今回の調査の過程で新たに検出された事項について、関連する会計処理を過年度に遡って訂正する必要があると判断した。また、これらの訂正に伴い、過年度において当該米国子会社の純資産が下落していた実態を踏まえて、当社の過年度の個別決算において関係会社株式評価損を計上する訂正を行った。このため、過去に提出済みの有価証券報告書などに記載されている連結財務諸表および財務諸表を訂正することとした。上記訂正による、各連結会計年度における財務数値への影響は、2025年1月期純資産において△8,224百万円。
⑦2025年8月27日に、「2025年8月26日に、東京証券取引所より2025年8月27日から特別注意銘柄に指定されることおよび上場契約違約金の徴求を受ける旨の通知を受けた。」と公表。2025年6月30日に同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を受領した旨を開示し、同日付けで過年度の決算内容の訂正を開示した。これにより、同社の主力事業であるネットワーク事業を担う海外子会社において、同社および本件子会社の一部の経営陣の関与のもとで、ソフトウェアのライセンス販売に係る売上高の過大計上および先行計上が行われ、また、本来は費用計上すべきソフトウェアの開発費がソフトウェア資産として過大計上されていたことが明らかになった。その結果、同社は、2021年1月期から2025年1月期第2四半期までの決算短信などにおいて、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2024年1月期の営業損失1,977百万円を105百万円、経常損失1,924百万円を12百万円、親会社株主に帰属する当期純損失2,231百万円を280百万円と過小に表示していたなど、決算内容を大幅に偽っていたことなどが判明した。また、特別調査委員会の調査報告書および日本取引所自主規制法人から同社に対する照会への回答などからは、本件不適切会計が2018年1月期から行われており、2018年1月期の各段階利益が6割以上減少し、2019年1月期および2020年1月期の各段階損益の赤字を黒字と表示していたことも判明した。さらに、同社は2020年2月に旧市場区分における当取引所マザーズ市場から市場第一部に市場変更しているところ、同社は当取引所に提出する書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、本件不適切会計により市場変更申請書類などの財務数値に関して不実の記載などを行ったうえで承認を得ていたことも判明した。以上のとおり、本件は、同社および本件子会社の一部の経営陣の関与のもとで長期間にわたり複数の不適切会計が行われた結果、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社は2025年6月30日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、未だ、同社の内部管理体制などについて改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとする。また、同社が、上記背景のもと投資判断情報として重要性の高い決算情報について長期間にわたり誤った情報を公表し続けたこと、および市場変更審査において、上場市場の変更申請に係る宣誓書に違反していながら市場変更の承認を得ていたことは、当取引所市場に対する株主および投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金4,800万円の支払いを求めることとする。特別注意銘柄指定期間は、2025年8月27日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、東京証券取引所が内部管理体制などの審査を行い、内部管理体制に問題があると認められない場合には指定が解除になる。一方で、内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となる。ただし、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制などが適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認められない場合(適切に運用される見込みがある場合に限る。)には、特別注意銘柄の指定を継続し、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日以降の審査までに、内部管理体制などの運用状況の改善を求められ、内部管理体制などが適切に整備され、運用されていると認める場合にはその指定が解除される。一方で、内部管理体制などが適切に整備され、運用されていると認められない場合には上場廃止となる。なお、内部管理体制などが適切に整備され、運用されていると認めるものの、経過観察の対象銘柄に該当する場合には、最長3事業年度、指定が継続され、その間同審査が行われる。
⑧2021年2月19日に、「村田製作所(6981)とACCESSは、幅広い業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現を推進するソリューションの開発および市場展開を目指して協業する。この取り組みの一環として、製造現場向けスマートものづくり支援ツール「JIGlet」(ジグレット)を共同開発し、2月19日より、両社の国内販路を通じて提供開始する。」と公表。国内製造業は、GDPにおいて全産業の2割程度を占め、雇用・イノベーションへの波及効果も大きい基幹産業である一方、グローバルで進展する工場のスマート化の流れに対して、「コストがかかるため導入ハードルが高い」「使い方が複雑で現場に定着しない」「費用対効果が分かりづらい」などの課題がある。この産業課題に対して、村田製作所の製造業におけるノウハウとACCESSのDX・IoT分野におけるコンサルティングおよびソフトウェア開発力を融合し、現場主導型の改善活動を後押しするものづくり支援ツールを展開していく。JIGletは、「1.作業ランプの点灯・消灯を検知する「照度デバイス」」、「2.ボタンを押して数をカウントする「ボタンデバイス」」、「3.任意の作業時に操作して時間を記録する「サイコロデバイス」」の3種類のデータ通信SIM内蔵センサーデバイスがあり、指一本で操作可能なデータ収集と可視化用画面、通知用チャットアプリから構成される。これらを用途により組み合わせて使うことで、ITの知識がない製造現場の担当者でも、簡単に設備や人の状態を記録・蓄積して工程のばらつきやムダをグラフで見える化でき、さまざまな改善活動や課題解決に活用可能。また、JIGletデバイスを既存設備に後付けできるため、大規模な設備導入・投資が不要で簡単に導入できる。
⑨社外取締役を除く取締役3名の報酬等の総額は14,937万円。単純平均で取締役1人当たり4,979万円。
株主総会での個人メモ
①取締役と監査役にミネラルウォーターが提供されていた。一方で、株主側には提供が無く、経営から株主へ議案を諮る場としては違和感。
⇒会社として、株主ではなく役員の方向を見ている様子が伺えた。不適切会計についてのお詫びのあった株主総会でもあり、会社の姿勢に違和感。
②株主総会の冒頭で、社長の大石清恭さんから、不適切会計により過年度の決算内容の訂正を行った件、東京証券取引所から上場契約違約金を請求された件、特別注意銘柄に指定された件などについて、説明とお詫びがあった。
③質疑応答で、「第2号議案の監査役選任の件について、9月12日に議案が公表された後、9月26日に改善計画の策定方針が公表され、その後直ぐ、9月30日に監査役が辞任し、10月15日に監査役候補に追加変更があった。前回の定時株主総会においても、監査役の辞任を見据えてなのか、直前になって監査役を1名追加したいとのことで議案の変更があった。外部から見ると監査役の体制がバタバタしているように見えるが、不適切会計の影響なのか?」との旨の質問あり。「監査役の古川雅一さんの9月30日の辞任は、個人的な事情。」との回答。
④議案の採決方法は拍手での採決。
⇒議決権の過半数を保有する大株主もいない状況で、出席者により保有している議決権数も違うので、デジタル時代に会場の拍手の多数で賛否を決めるのでは基準が曖昧に感じる。投票方式を採用したりして、その場で数字で示したほうが株主総会に出席している株主から見て納得感がある。
株主総会を終えて感じたこと
株主総会時点、株式は未保有ですが、今回、実際に社長や取締役を間近に見てその振る舞いを確認できたこと、会社の雰囲気を感じられたことが株主総会に参加した大きなメリットでした。
株式分割後の基準で、2006年には株価が11,800円をつけたこともある、記憶に残る企業です。
また、清原達郎さんが筆頭株主として33.3%を保有しており目を惹きますが、まずは、不適切会計からの信頼の回復と、特別注意銘柄から解除され上場が維持できるのか注視します。
監査役の選任議案については、前回の定時株主総会に続いて議案の公表後に変更があり、不祥事を起こした会社でもあることから、さらなる問題が潜んでいないかやや気になるところです。
2021年1月期より5期連続で赤字が続いていますが、早期の黒字化を期待しています。再投資も検討します。