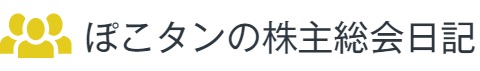ヴィア・ホールディングス 臨時株主総会
日時:2025年9月30日(火) 10:00-10:50
場所:リーガロイヤルホテル東京(都電荒川線早稲田駅徒歩3分)
出席株主数:約50名
お土産:無し、ペットボトルのお茶の配布あり
企業概要
ヴィア・ホールディングス(7918)
①「やきとりの扇屋」「備長扇屋」「紅とん」「パステルイタリアーナ」「いちげん」などの飲食店を展開する外食サービス事業を運営。
②筆頭株主は、アサヒグループホールディングス(2502)の子会社のアサヒビールで、319万株、6.9%を保有。
第2位の株主は、横川竟さんの配偶者の横川てるよさんで、214万株、4.7%を保有。
第3位の株主は、すかいらーく創業者の横川竟さんで、202万株、4.4%を保有。
第4位の株主は、元社長の横川紀夫さんで、横川紀夫さんが代表を務めるウェルカムの保有分も含めると、257万株、5.6%を保有。
第5位の株主は、清酒などのアルコール飲料などの製造販売を手掛ける大関で、61万株、1.3%を保有。
③株主優待(3月末)
100株:株主割引券5,000円
300株:株主割引券10,000円
600株:株主割引券15,000円
1,000株:株主割引券20,000円
5,000株:株主割引券30,000円
10,000株:株主割引券40,000円
株式情報
時価総額:51億円(2025年9月29日時点)
売上高:173億円(2025年3月期実績)⇒177億円(2026年3月期予想)
株価:112円(2025年9月29日時点)
1株純資産:△84.3円(2025年6月末時点)、PBR:債務超過ではないものの、種類株主からの払込金額および優先配当予定額を控除して計算しているためマイナス
1株当期純利益:2.41円(2026年3月期予想)、PER:46.4倍
1株配当:無配(2026年3月期予想)、配当性向:無配
配当利回り:無配
株主数:51,972名
会計基準:日本会計基準
株主総会前の事前情報
①2026年3月期第1四半期は、外食産業においても、インバウンドを含めた需要は回復基調にあるものの、深刻な人手不足やコスト負担の増加など、厳しい経営環境が継続している。このような環境のなか、当社グループは、人手不足やコスト上昇、事業環境の変化といった課題に対応すべく、収益構造の改善に注力している。具体的には、メニュー改定および構成の見直しによるお客様一人あたりの付加価値向上、食材ロス削減などによる原価管理、店舗オペレーションの再設計による調理・接客の生産性向上などを進めてきた。また、「本質回帰」をキーワードに、主力商品である「焼鳥」など各業態の看板商品の品質向上にも取り組み、顧客満足度の向上にも取組んでいる。人的資本への投資についても、社員給与のベースアップや研修制度の拡充、外国人材の採用強化、多様な人材が活躍できる組織づくりなど、「社員を豊かに幸せにできる会社」を目指した取組みを継続している。
⇒政府による外国人受け入れ政策の見直しの動きもあり、労働力不足対応への影響が気になるところ。
②これらの施策の結果、当第1四半期は、前年同期比で客数はわずかに減少したものの、商品の魅力強化やメニューの見直しなどにより売上高は前年同期を上回る水準で推移した。一方で、物流費や食材調達コストの上昇が収益を圧迫し、営業利益・経常利益は減益となった。引き続き、コストバランスの最適化を図りつつ、サービス品質および料理の提供品質のさらなる向上に努め、既存店における客数の持続的な増加と、大都市圏への新規出店により企業価値の向上を目指していく。店舗数については、閉店が1店舗となり、当第1四半期末の店舗数は、304店舗(うち、FC29店舗)となった。以上の結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの売上高は4,346百万円(前年比0.3%増)、営業利益は16百万円(前年比86.3%減)、経常利益は2百万円(前年比97.5%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は46百万円(前年比0.8%増)となった。
③2025年8月12日に、中期経営計画2028を公表。2028年3月期に、売上高22,400百万円、営業利益900百万円。店舗数は、現状レベル(308店舗)の309店舗。
④2025年8月12日開催の取締役会において、2024年1月5日に野村證券株式会社を割当先として、第三者割当により発行した第26回、第27回新株予約権について、2025年8月27日(予定)に残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちにその全部を消却することを決議。当社の株価が下限行使価額を下回る期間が長期化していることから、本新株予約権の行使が行われず、当初想定していた資金調達の規模を実現することが困難となった。今後の資本政策の柔軟性を確保するため。
⑤2025年8月12日開催の取締役会において、同日付で開示のE種優先株式の発行に係る払込みがなされることを条件として、当社発行のC種優先株式の一部を取得することを決議。2021年5月20日に、新型コロナウイルス感染症拡大による厳しい経営環境下において、財務体質の抜本的な改善と事業・キャッシュフローの正常化を図るため、総額15億円のC種優先株式を発行した。当社グループは、2021年4月20日公表の「事業再生ADR手続の成立及び債務の株式化等の金融支援に関するお知らせ」に記載の事業再生計画の下、収益体質の強化と財務体質の抜本的な改善に取り組み、新たな資金調達の見通しも確保できている。こうした状況を踏まえ、今後の財務体質の安定化を目的に、優先配当負担の軽減を図るため、C種優先株式の一部取得を実施することとした。取得予定日は2025年10月3日。取得する株式の総数750株、株式の取得価額の総額787,179,263円。取得後の未取得株式数は750株。
⑥2025年8月12日開催の取締役会において、「第三者割当によるE種優先株式および第28回新株予約権の発行、定款の一部変更、ならびに資本金及び資本準備金の額の減少」について決議。
グロースパートナーズが管理・運営するファンドであるGP上場企業出資投資事業有限責任組合に対し、総額15億円(1株100万円で1,500株)のE種優先株式を第三者割当の方法により発行する。普通株式の転換価額は83円(2025年8月8日までの直前16取引日の終値の単純平均値(117.6円)の70%に相当する金額)。優先配当率は年3.0%に設定。調達資金15.0億円の使途は、新規出店投資3.0億円、生産性向上投資1.0億円、C種優先株式の償還7.8億円、事業拡大のためのM&A2.9億円。
GP上場企業出資投資事業有限責任組合に対し、第28回新株予約権を第三者割当の方法により発行する。割当日2025年10月3日とし、発行新株予約権数181,000個(1,810万株)を割当。行使価額は83円。調達資金の額は15.1億円。行使期間は、2025年10月4日から2030年10月3日まで。調達資金15.1億円の使途は事業拡大のためのM&A。
1,809百万円は、M&A待機資金とし、2031年3月末日までに当社グループの事業拡大に資するM&Aに充当する予定。規模感としては1件につき数店舗から数十店舗の案件を複数実施する想定。
⑦E種優先株式については、普通株式を対価とする取得請求権が付されているが、E種優先株式の全部についてこの取得請求権が行使された場合、普通株式18,072,289株が交付され、その議決権数は180,722個となる(2025年3月31日現在の当社の発行済株式総数45,634,213株に対する比率は39.60%、議決権総数456,151個に対する比率は39.62%)。なお、交付される普通株式の数については、E種優先株式に優先配当金に未払が生じないと仮定して、払込金額の総額を転換価額で除した数として算出している。また、本新株予約権の目的となる株式数は18,100,000株であり、同株式に係る議決権の数は181,000個であるため、全ての本新株予約権が行使された場合には、2025年3月31日現在の当社の発行済株式総数45,634,213株に対する比率は39.66%、同日現在の当社の議決権総数456,151個に対する比率は39.68%となる。以上より、E種優先株式の転換が行われた場合の潜在株式数ならびに本新株予約権に係る潜在株式数を合計した希薄化率は、2025年3月31日現在の当社の発行済株式総数45,634,213株に対して79.27%、議決権総数456,151個に対して79.30%となり、本第三者割当により大幅な希薄化が生じる。
⑧2025年8月末時点、C種優先株式残は、RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合に対する1,500株(1株100万円、15億円)。優先配当率は年8.5%。転換価額は、2022年3月31日以降の毎年3月31日および9月30日に転換価額修正日に先立つ30連続取引日の終値の平均値の90%に相当する金額。下限転換価額は103円。
D種優先株式残は、りそな銀行に対する2,674株(1株100万円、26.7億円)、横浜銀行に対する496株(1株100万円、4.9億円)。優先配当率は年2.0%。転換価額は、2022年3月31日以降の毎年3月31日および9月30日に転換価額修正日に先立つ30連続取引日の終値の平均値の90%に相当する金額。下限転換価額は154.5円。
⑨2020年12月10日に、一般社団法人事業再生実務家協会に対し、事業再生ADR手続の正式な申込みを行い、同日付で受理され、同日付で一般社団法人事業再生実務家協会と連名にて、取引金融機関に対して、借入金の残高維持を求める一時停止の通知書を送付。事業再生ADR手続は、取引金融機関のみを対象に進められる手続であり、現在当社グループと取引をいただいている一般のお取引先(お客様、仕入れ先など)の皆様には、影響を及ぼすものではない。当社は、事業再生に向けた計画の策定を、公平中立な立場にある第三者の調査・指導・助言をいただきながら行うことで、計画の合理性と手続の透明性を確保するスキームとして、新型コロナウイルス感染症による混乱期においては有用な手段と判断して事業再生ADR手続を採用した。
2021年4月20日に事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の決議のための債権者会議(第3回債権者会議)において、対象債権者たるすべての取引金融機関の皆様から同意をいただき、同日をもって本事業再生ADR手続が無事に成立した。
※事業再生ADR:
事業再生の法的整理と私的整理のメリットを組み合わせ、裁判外手続き(ADR)によって債務者の事業再生を図る制度。具体的には、中立の立場に立つ第三者が、過剰債務を負う債務者と金融機関などの債権者との調整を行い、事業再生計画を策定する制度のことで、法的手続きを避けつつ事業価値を修復し、債権者と債務者の合意に基づいて債務の猶予・減免などを行い、経営困難な企業の再建を目指すものである。通常の商取引と併行して進められるので、負担軽減が期待できる一方で、会社の信用保持にも寄与でき、第三者機関が介在するためトラブルを回避でき、公平性・信頼性が担保されるため、事業を迅速に再構築したい場合に向いた制度といえる。
⑩社外取締役を除く取締役4名の報酬等の総額は4,700万円。単純平均で取締役1人当たり1,175万円。
株主総会での個人メモ
①質疑応答で、「優先株式の発行と新株予約権の発行により調達する資金のうち、18億円をM&Aに活用するとの説明があった。一方で、同時に公表した中期経営計画では、店舗数について、2025年3月末308店舗、2028年3月末309店舗となっており、店舗数が変わらない。M&Aによる店舗数はどのように反映されているのか?」との質問あり。「中期経営計画の店舗数は、既存店舗数の推移を掲載している。別枠としてM&Aによる店舗数が増える。」との旨の回答。
②質疑応答で、「普通株式においても、1円でもよいので早く配当を出して欲しい。」との意見あり。「復配については重要な課題。時期は言えないが、一刻も早く復配ができるように経営努力をしていく。」との説明。
③質疑応答で、「優先株式が普通株式に転換されたり、新株予約権が行使されると株数が大幅に増える。以前、株主優待が改悪された記憶もあり、株数が増えることにより株主優待が改悪されないか心配。今後の株主優待の方針を教えて欲しい。」との旨の質問あり。「株主優待は極めて重要な制度なので大切にしていきたい。かつては相当厚い優待を出していたこともあったが、業績悪化により見直しをした。ここ数年は少しずつ拡充している。この方針に変わりは無く、面白い株主優待にしていきたい。現時点、株主優待の廃止は考えていない。」との回答。
④質疑応答で、「M&Aについて、重きを置くポイントは収益性なのか、ジャンルなのか?M&Aの方向性を教えて欲しい。」との質問あり。「世の中の変化が速い一方で、人口減少は避けられない。新たな収益となる柱がもう1つ2つ欲しい。優先順位として、まず、収益力の強化が図られること、その次に、既存の事業とのシナジーがはかられること。」との説明。
⑤質疑応答で、「株主優待について、割引率が25%⇒50%へ拡充されたが、以前のように100%まで上げて欲しい。」との意見あり。「収益力を回復して、工夫をして、面白い、株主に喜んでもらえる株主優待にしていきたい。」との旨の回答。
⑥質疑応答で、「グロースパートナーズとの事業提携について、タイムラインやゴールを教えて欲しい。」との質問あり。「まず、3年先を見て事業提携している。ファンドとしての出資期間もあると思うが、次の方向性が見える状態に持っていきたい。」との旨の説明。
⑦質疑応答で、「新規出店に対応する人材確保はどうするつもりなのか?」との質問あり。「2028年3月まで、店舗数は微増の計画。スクラップ&ビルドにより、既存店の人材を新店舗に活用する。採用もそこそこできている。政府による外国人規制の話も出てきているが、外国人の正社員も増えている。」との旨の回答。
⑧議案の採決方法は拍手での採決。
⇒議決権の過半数を保有する大株主もいない状況で、出席者により保有している議決権数も違うので、デジタル時代に会場の拍手の多数で賛否を決めるのでは基準が曖昧に感じる。投票方式を採用したりして、その場で数字で示したほうが株主総会に出席している株主から見て納得感がある。
株主総会を終えて感じたこと
株主総会時点、株式は未保有ですが、今回、実際に社長や取締役を間近に見てその振る舞いを確認できたこと、会社の雰囲気を感じられたことが株主総会に参加した大きなメリットでした。
質疑応答では、社長の楠元健一郎さんが丁寧に回答対応されていました。一方で、今後、E種優先株式の普通株式への転換や、第28回新株予約権の行使により、議決権総数対する希薄化率が最大で79.30%になる可能性もあり、1株あたりの価値の希薄化が気になります。
中期経営計画などにおいて、外国人材の採用強化も掲げていますが、社長の楠元健一郎さんが質疑応答で触れられていたように、政府による外国人受け入れ政策の見直しの動きもあり、今後の人手不足対応への影響(外国人に頼りすぎるリスク)が気になります。
移民政策で先行する国々においては、政権基盤を揺るがす事態にもなっており、良し悪しは別として、遅かれ早かれ外国人受け入れ政策に大きな変化点が出てくるかもしれません。
また、現状、日銀の政策金利の見直し遅れ(ビハインド・ザ・カーブ)などもあり、物価が安定せず、体感として、過度なインフレが継続しているように感じます。特に年金のマクロ経済スライド(賃金や物価による改定率から、現役の被保険者の減少と平均余命の伸びから算出したスライド調整率を差し引き調整)により、インフレの影響を強く受けるボリュームゾーンの年金世帯を中心とした需要減も心配です。
黒字決算の定着を期待していますが、まずは前期の最終赤字から、今期、業績予想通り最終黒字へ回復できるのか、継続注視します。「魚や一丁」「ステーキハウス松木」「焼肉扇屋」などの魅力的なブランドもあり、再投資も検討します。