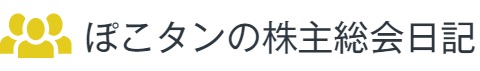スミダコーポレーション 第70期定時株主総会
日時:2025年3月26日(水) 13:00-14:25
場所:東京會舘(日比谷駅直結)
出席株主数:約50人
お土産:無し
企業概要
スミダコーポレーション(6817)
①音響・映像・OA・車載用・産業用機器等の電子部品、高周波コイルの研究・開発・設計・製造・販売を、地域別に「アジア・パシフィック事業」(売上構成比63%)と「EU事業」(売上構成比37%)として運営。
②取締役の八幡滋行さんが取締役を務めるヤワタビルが、第3位の株主で、同じく取締役を務めるYawata Zaidan Limitedの保有分を含めると、187万株、5.6%を保有。
株式情報
時価総額:329億円(2025年3月25日時点)
売上高:1,439億円(2024年12月期実績)⇒1,440億円(2025年12月期予想)
株価:995円(2025年3月25日時点)
1株純資産:1,774円(2024年12月末時点)、PBR:0.56倍
1株当期純利益:96.8円(2025年12月期予想)、PER:10.2倍
1株配当:53円(2025年12月期予想)、配当性向:54%
配当利回り:5.3%
株主数:22,697名
会計基準:IFRS
株主総会前の事前情報
①米国においては、インフレが減速に向かう中、底堅い賃金上昇により消費が好調。欧州においては、自動車を中心に域外への輸出が伸び悩んでおり、とりわけ中核国ドイツの製造業景況感が悪化している。中国においては、不動産不況が長引いており、住宅ローン金利の引き下げなどの政策の効果も限定的で依然として内需は停滞している。金融政策においては、米国FRBがインフレ圧力の緩和を受けて計1.0%の利下げを実施し、また欧州ECBもそれを上回る利下げを実施した。一方で、日銀は3月にゼロ金利を解除した後、7月にも利上げを実施した。これらを受けて、年初からの円安基調は反転し、第3四半期連結会計期間においては円高が進行した。その後、11月の米国大統領選挙の結果を受けて、米国における長期金利の上昇などにより、年末にかけて再び円安が進行した。
②電子部品業界は、コロナ後の需要増加と供給不安が重なり在庫が膨らんでいたが、ようやくこれらの在庫が解消に向かい出荷が増加傾向にあると見ている。世界の自動車販売は、供給制約によるペントアップ需要の消化が進む中、自動車ローン金利の高止まりなどを受けて車両価格が上昇していることから、消費者が自動車を買いづらい状況が継続している。EVについては、米国において補助金支給要件が厳格化され、またドイツにおいて補助金が打ち切られるなどの環境下で、これら地域における需要が低迷した。米欧の自動車メーカー各社がEVへの投資時期を遅らせることなどを発表したことに呼応する形で、EVの普及を後押しする急速充電ネットワークの構築においても投資を手控える動きが見られた。一方で、xEVの最大市場である中国においては、メーカー各社が値引きを強化したことや政府による買い替え促進政策などを受けて、販売台数は引き続き堅調。2025年に入り米国においてEV促進策が撤回された影響も注視している。
③当社グループでは、計画期間を2024年から2026年までの3か年とする中期経営計画を2024年2月に発表した。本中期経営計画においては、脱炭素化の流れを事業機会と捉え、xEV関連、充電インフラ、太陽光発電、蓄電池などを含む用途群を「グリーンエネルギー関連」と定義し、重点分野と位置づけて更なる成長を目指すことを掲げている。また、地政学リスクの高まりに対処するため、営業、開発、製造の3体制を各地域で完結し、お客様のニーズにより柔軟かつ迅速に対応できる地産地消の体制づくりを進めている。具体的には、中国における生産能力の最適化、北米における研究開発能力の更なる増強、インドにおける新規案件の獲得およびベトナムでの生産能力の拡大などを進めている。
④当連結会計年度においては、獲得済み案件を積み上げて作成した増収計画に基づき、3期連続となる最高益更新を掲げた。しかしながら、EVに対する様子見姿勢および高金利を受けた投資の手控えなどの影響を受け、期初に想定していた売上収益拡大が遅れた。最大限の費用抑制努力を継続しているものの、減収による影響を完全に吸収することは難しいと判断したため、7月31日にやむなく業績予想を下方修正した。しかしながらその後も、特に欧州における車載関連市場・インダストリー関連市場の回復に想定以上の時間を要したため、大胆な構造改革を速やかに実施する必要があると判断した。構造改革の内容は欧州拠点における人員削減による合理化。本合理化により、当連結会計年度に退職一時金などに係る事業構造改革費用1,086百万円をその他営業費用として計上したが、2025年12月期に約1,600百万円、2026年12月期以降に1年あたり約1,800百万円の費用削減効果を見込んでいる。
⑤当社グループはカスタム製品の受注生産ビジネスを営んでいるため、獲得した案件には供給責任が発生する。当連結会計年度においては、過年度に引き続き増収を見越して設備および人員を配置していたものの、売上が実現せず結果として固定費負担が増えて収益性を低下させてしまった。現在、全社を挙げて損益分岐点の引き下げを進めている。前述した外部環境の変化を受けて、売上の成長は鈍化が懸念される。このため、足元の逆風下で現実的に見込まれる売上の中で、目標とする利益を出せる体制に変えていく方向に、戦い方を変える判断をした。欧州での構造改革はこの一環。加えて、主要な製造拠点である中国においても退職者の補充を行わない形で間接人員の適正化を進めている。また、業務効率化のため営業や生産技術の組織体制を変更した。
⑥当連結会計年度における当社グループの業績は、売上収益は、車載関連で様々な用途の製品需要が堅調に推移した一方で、インダストリー関連で太陽光発電関連および産業機器向けの需要が低下したこと、家電関連でノートパソコン、タブレット端末、スマートフォン関連の需要が低下した。グリーン関連売上は大幅な成長を見込んでいたが、xEV関連需要の失速を受け微増にとどまった。当連結会計年度の売上収益は前年比2.5%減の143,978百万円。営業利益は、前年との比較において、減収による影響(3,465百万円の減益)、生産数量の減少に伴う固定費負担増加による影響(1,178百万円の減益)、並びに欧州における事業構造改革費用1,086百万円などの影響を受けて、同47.3%減の4,513百万円となった。また、税引前当期利益は同77.9%減の1,295百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は同88.3%減の590百万円。
⑦アジア・パシフィック事業では、車載関連が堅調に推移した一方で、中国の景況感の悪化を受けてインダストリー関連の需要が減退したことも影響し、売上収益は前年比1.1%減の94,679百万円。不断の生産効率改善ならびに経費節減に取り組んでいるものの、工場の操業度低下が利益の圧迫要因となり、セグメント利益は同42.0%減の3,146百万円となった。
⑧EU事業では、前年に比べ円安/ユーロ高で推移したものの、家電関連およびインダストリー関連での減収影響により、売上収益は前年比7.9%減の56,240百万円。時短勤務をはじめとする経費節減に努めたものの、現下の厳しい市場環境は当面続くとの判断から人員削減による合理化が必要と判断し、構造改革に係る一時金を計上した。セグメント利益は同33.5%減の2,679百万円。
⑨車載関連は、世界的な新車生産台数の伸びを背景に、xEV関連およびその他用途群の売上が好調に推移した。しかしながら、欧州におけるEVへの補助金打ち切りの影響や、米国における政策の行方を注視している。車載関連の売上収益は前年比1.2%増の87,893百万円。
⑩インダストリー関連は、米欧のEVシフトにややブレーキがかかる動きもある中で、当社グループにおいてはxEV向け急速充電インフラ関連などが成長した。他方で、長引く高金利などの影響を受けて太陽光発電関連の投資を手控える動きが顕著になったこと、ならびに中国の景況感が停滞したことなどにより当社グループの製品需要が減退した。インダストリー関連の売上収益は前年比9.5%減の36,314百万円。
⑪家電関連は、ノートパソコン、タブレット端末、スマートフォン関連の需要が引き続き弱含みで推移したものの、足元では生成AI搭載モデルの販売開始などもあり、需要回復の兆しが見えてきている。家電関連の売上収益は前年比4.4%減の19,770百万円。
⑫当連結会計年度末現在、短期有利子負債(1年内返済予定または償還予定の長期有利子負債を含む)の残高は36,424百万円で、長期有利子負債の残高は16,004百万円。なお、借入金のうち約70%が変動金利、約30%が固定金利によるもの。保有する資産のうち大部分が外貨建てであることに対応し、為替の影響を少なくするため、現地通貨建てでの調達を原則としつつ、金利コストも考慮した最適な資金調達を行っている。外貨建て借入金の割合が借入金全体の約82%を占めており、借入金の平均金利は4.3%。 当社グループでは、主要な銀行と定期的にミーティングを行い、良好な関係を築いている。銀行団のオープン・コミットメントラインは110億円を維持しており、これら全てが未使用。なお、中期的には収益性の向上と財務体質の強化に取り組み、信用格付けを取得し、資金調達の方法についての選択肢を増やす目標を持っている。
⑬当社グループはB-to-Bビジネスを営んでいるため、DSO(売上債権回転日数)の短縮、つまり営業債権の回収期日の短縮は顧客からの値下げ圧力になりかねない。同様に、DPO(仕入債務回転日数)についての取り組みも仕入先からの値上げ圧力になりかねない。したがって、DIO(在庫回転日数)の管理が現実的な取り組みとなっている。DIOはサプライチェーンの混乱などのため顧客から納品の先延ばし要請を受けた影響で、2022年6月末時点で116日まで伸びた。その後、地域別、会社別に毎月モニタリングを実施し棚卸資産を減らす取り組みを行い、当連結会計年度末のDIOは85日となった。当連結会計年度末のDSOは73日、DPOは63日。
⑭設備投資額は、2023年98.0億円→2024年78.6億円。2024年は売上に直結する設備投資は継続し、それ以外の投資は可能な限り後ろ倒しさせた。2025年の予想は86.0億円。
⑮景気循環や関税およびEVに対する補助金などの政策などにより短期的な需要の増減は想定されるものの、中長期的には、世界で脱炭素の流れは不可逆であると見ている。このメガトレンドは当社グループの事業にとり、車載関連市場におけるxEV関連需要の拡大およびインダストリー関連市場におけるグリーンエネルギー関連需要の拡大に寄与すると期待している。また、利益面では急激な為替変動や原材料価格の変動の影響が考えられる。2025年12月期通期の売上収益は144,000百万円を見込んでいる。利益については、営業利益は7,000百万円、税引前利益は4,080百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は3,200百万円、基本的1株当たり当期利益は96.83円となる見通し。業績見通しの前提となる為替レートは、米ドルは145.0円、ユーロは159.5円、人民元は20.40円を想定している。また、銅価格は1トン当たり9,500米ドルと想定している。
⑯2025年2月7日開催の取締役会において、配当政策の変更を決議。連結配当性向30%以上を勘案した配当を実施することを基本方針とし、実際の連結業績により、この基本方針による配当が適切でない場合には、株主資本配当率(DOE)3%なども考慮した上で、剰余金分配可能額の範囲で株主還元の充実を図っていく。2025年12月期から適用。
⑰2024年2月8日に、新中期経営計画(2024-2026)を公表。2026年12月期に、売上高1,900億円、営業利益135億円、EPS 272円。
⑱取締役候補者8名中、70歳以上の候補者は八幡滋行さん(1951年生まれ、73歳)、范仁鶴さん(1949年生まれ、75歳)の2名。役員定年制(一般的には65歳~70歳)を設定して、未来のために次世代育成を進めたほうがよいと思う。
⑲社外取締役を除く取締役名と執行役7名の報酬等の総額は15,700万円。2024年3月に退任した1名を3ヶ月分、同月に就任した3名をそれぞれ9ヶ月分として試算すると、単純平均で取締役1人当たり2,854万円。
株主総会での個人メモ
①取締役全員にミネラルウォーターが提供されていたが、株主側には提供が無く、経営から株主へ議案を諮る場としては違和感。会社として、株主ではなく役員の方向を見ている様子が伺えた。
②質疑応答で、「在庫削減中とのことだが、現有の設備能力に対し、現在の稼働率はどの程度なのか?」との質問あり。「70%程度。」との回答。
③質疑応答で、「PBRが0.5倍程度と低迷しており、市場から評価されていない。評価されていない理由は何だと考えているのか?」との質問あり。「稼ぐ力、業績の安定性、業績の成長性の3つが必要だが、稼ぐ力に一番課題があると考えている。また、BtoBの事業なので、投資家から見て分かりにくいと思うので、分かりやすい説明をしていく。」との旨の説明。
④質疑応答で、「中期経営計画の達成見通しは?」との質問あり。「2026年12月期の営業利益135億円は、正直に言ってなかなか難しい。近づける努力をする。」との回答。
⑤質疑応答で、「中国のローカルEVメーカーへの取り組み状況は?」との質問あり。「既にトップEVメーカーと取引している。手を緩めずに取り組んでいく。」との説明。
⑥質疑応答で、「知的財産について、特許件数が少ない印象。出願数増のため、開発者へのインセンティブを設けたほうが良いのでは?」との質問あり。「大学との共同研究に注力している。件数は徐々に伸びており、今後も努力していく。良い特許の出願者に対し、報奨金を出しており、金額についても昨年見直しし増額した。」との回答。
⑦質疑応答で、「設備投資について、新しいビジネスと設備更新の割合を教えて欲しい。」との質問あり。「2024年12月期は、新製品と増産対応で、全体の約7割。2025年12月期は、設備投資額86億円のうち、新製品と増産対応で50.5億円を予定している。」との説明。
⑧質疑応答で、「有利子負債が多く、金利負担が多い。財務基盤が弱く、配当の継続性が心配。」との意見あり。「為替の影響を考慮して、約8割を外貨で調達している。財務の健全性は悪くは無いとの理解。配当の継続性には、稼ぐ力が重要となる。稼ぐ力を高めることが急務。損益分岐点を下げる。」との回答。
⑨質疑応答で、「防衛関連分野への取り組みは?」との旨の質問あり。「兵器はやらない。ハイブリッド装甲車、ハイブリッド船舶、基地の電源などはビジネスとしてやっていきたい。車関連が多いので、ボラを下げるため、医療などのビジネス分散が必要。ただ、データセンターは価格競争が厳しい。」との旨の説明。
⑩質疑応答で、「ほとんどの質問について、担当役員が回答をしているが、議長である八幡滋行さんの意見を伺いたい。」との意見あり。「監督機能と執行機能を分けているので、執行側からの説明を中心とした方が良いと思っている。」との旨の説明。
⑪質疑応答で、「カスタム品ビジネスとのことだが、最低受注数の取り決めなど、受注時のリスク管理は対応しているのか?管理プロセスも教えて欲しい。」との質問あり。「最低数量保障、設備投資の償却費を契約に落とす努力をしている。受注を取る際に、数量が伸びそうな案件を取る努力をしている。営業部門とビジネスユニットで協議してリスク管理をしている。多くの案件で代表執行役の堀寛二さんに承認依頼が回ってきている状況。」との回答。
⑫質疑応答で、「「中国における生産能力の最適化」の具体的な内容は?」との質問あり。「受注に合わせて人員調整をするとの意味。」との説明。
⑬質疑応答で、「中国での社内不正への取り組みは?」との質問あり。「全ての海外拠点において、グローバルコンプライアンスマニュアルを用いて教育している。日本人を含めた組織づくりをしている。」との回答。
⑭質疑応答で、「市況として、半導体、パワーデバイスの需要が弱い。今期の設備投資額を強気で計上している根拠はあるのか?」との質問あり。「EVは、どのメーカーも完全には止めていない。中国は頑張っている。一定数は出ていくと思っている。カスタム品なので、需要が紐付いた設備投資計画となっている。」との説明。
⑮質疑応答で、「配当の財源は確保されているのか?」との質問あり。「配当原資はフリーキャッシュフロー。配当を十分上回るフリーキャッシュフローを確保できると考えている。」との回答。
⑯質疑応答で、「八幡滋行さんの保有株式数が0の理由は?」との質問あり。「個人での保有は無いが、ヤワタビルとYawata Zaidan Limitedで、約5%を保有している。」との説明。
⑰質疑応答で、「執行役にストックオプションが付与されている一方で、取締役に付与されていない理由は?」との質問あり。「監督機能である取締役と、執行役を分けた組織としているので、そのような対応となっている。」との旨の回答。
⑱質疑応答で、「「対象となる執行役1名および社内取締役2名に対してフリンジ・ベネフィット総額13百万円(うち当社負担分12百万円)を支払った」とあるが、どのような内容なのか?」との質問あり。「医療保険。」との説明。
※フリンジベネフィット:企業が役員や従業員に対して給与以外に提供する経済的利益。
⑲議案の採決方法は拍手での採決。議決権の過半数を保有する大株主もいない状況で、出席者により保有している議決権数も違うので、デジタル時代に会場の拍手の多数で賛否を決めるのでは基準が曖昧に感じる。以前のように投票方式を採用したりして、その場で数字で示したほうが株主総会に出席している株主から見て納得感がある。
株主総会を終えて感じたこと
株主総会時点、株式は未保有ですが、今回、実際に取締役を間近に見てその振る舞いを確認できたこと、会社の雰囲気を感じられたことが株主総会に参加した大きなメリットでした。
議長は、取締役の八幡滋行さんが務められていましたが、咳き込む場面が多く、体調が気になりました。質疑応答で指摘があった通り、質問に対してほぼ担当の執行役員が回答していましたが、八幡滋行さんの監督機能としての補足意見ももっと多く伺いたかったです。なお、多くの質問が出ていましたが、質問が尽きるまで対応されていたのは、良い対応だと思いました。
2023年3月に、東京証券取引所が「PBR1倍割れの企業に改善要請」を実施しましたが、スミダコーポレーションは、1株当たり純資産1,774円に対し、株価が995円(2025年3月25日時点)、PBR0.56倍と低迷しており、PBR1倍達成に向けた施策が求められます。
なお、スミダコーポレーションはIFRSを採用していますが、のれんおよび無形資産の一部などには償却が発生しないので、日本会計基準を採用している企業と比べる際には、利益や純資産への影響を考慮する必要があり、また、万が一、業績が悪化したときのまとまった減損損失も心配です。のれんおよび無形資産の状況には継続注視が必要です。
中国の地政学リスクが気になり、EVの雲行きも怪しく、当面は予断を許さない事業環境だと思います。質疑応答で説明があった通り、中期経営計画の達成も難しそうです。一方で、配当利回りには魅力を感じるので、再投資も検討します。
2024年3月26日に出席したスミダコーポレーションの株主総会の内容についてはこちら↓
スミダコーポレーションの株主総会に出席しました【2024年3月26日】 | ぽこタンの株主総会日記